教科紹介
各教科の特色
主体的な学びを育む、西武台千葉の特色

国語
自分の考えを表現する力を養う
総合的な言語能力の獲得をめざし、文章を読み取る力はもちろん、与えられた条件や図表から得られる情報を処理する力と、そこから得られた自分なりの考えを表現する力を養います。

数学
『ひらめく力』がある大人に
数学を学んだ経験は社会に出ても役に立つと考え、数学の面白さ、楽しさを感じられるように授業を展開していきます。考えて、考え抜く力を鍛錬し、『ひらめく力』を育みます。

英語
アウトプット中心の授業
英語をコミュニケーションのツールとしてとらえ、多くの場面でグループワークを取り入れて、学習したことを口頭や文章にして発表するという授業を展開しています。

物理
難しいけど面白い
受験に必要な知識の取得に終わることなく、「なぜ?」「なるほど!」を体感できる指導を展開し、「難しいけど面白い」を目標に自然現象の本質と原理に迫ります。

生物
40 億年の成果
生物の40 億年の工夫と試み、幸運と不運の積み重ねの末に得た成果としての生命現象を率直にとらえ、そのしくみを丁寧に学ぶことにより、生物の営みの基本原理の理解と定着を目指します。

化学
自分の言葉で表現する
結論のみを暗記するのではなく、そこに至るまでの過程を自分の言葉で表現できることが肝要です。表面的な知識だけでなく、現象や原理について論理的に考察できる力の養成を目ざします。

日本史
物語でとらえて思考力を養う
ラテン語のhistoria には「歴史」と「物語」の両方の意味があります。学力の3 要素「思考力・判断力・表現力」を高めていくためにも、歴史のつながりを物語でとらえ、歴史的思考力を高めていきます。

世界史
好きになれば、
あとは高みに昇るだけ
「好きだ」と感じたら、世界史マスターへの扉が開かれたも同然です。大学受験でもその興味こそが強力な武器となります。共に楽しみ、探求し、「世界史」への造詣を深めていきます。
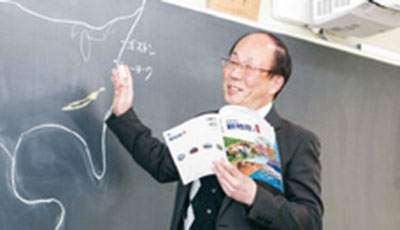
地理
仕組みがわかれば
同じ気候には共通する条件があります。人々の暮らしにも規則があります。仕組みがわかると興味が深まり、楽しく学べ、理解も深まります。知らない場所のことも条件や規則が わかっていれば、おのずと見えてくるものがあるはずです。
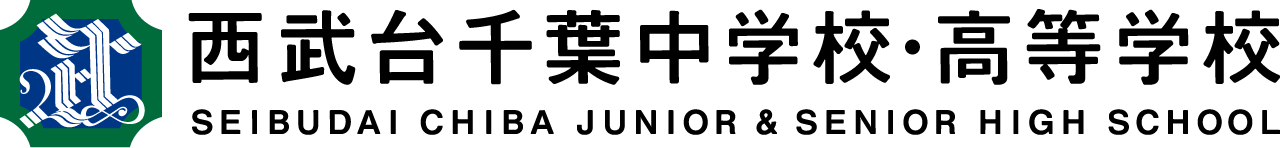
 西武台千葉中学校・高等学校
西武台千葉中学校・高等学校
